Image may be NSFW.
Clik here to view.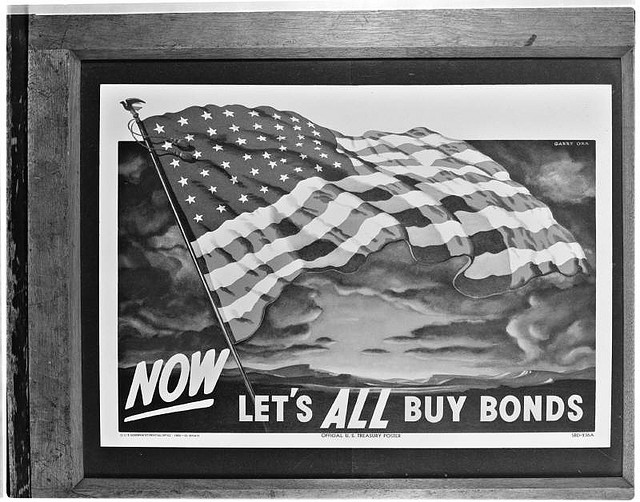
by courtesy of Metro Library and Archive
長期社債の発行が急増しているようです。
国内企業の社債発行が活発になってきた。なかでも満期まで10年以上と長い期間の社債を発行する動きが目立つ。年央に大きく動いた長期金利が落ち着いてき た一方、市場では金利の先高観もくすぶる。このため、低金利の今のうちに長期資金を手当てしておこうという企業が増えている。(2013年9月4日付 日経新聞朝刊)
要は、今後金利が上昇するだろうから、低金利の今のうちに必要資金を調達しておこうという考えのもと、大手企業が社債の発行を増やしているということです。藤巻健史さんの言う
金利上昇時→短い運用・長い調達
という理論を、そのまま適応したことになります。
将来金利が上昇するのか、それとも下降するのかは、人によって予想は違うでしょう。個人的には、2%インフレを日銀が目標にしている以上、名目金利は理論上上昇するので、長期金利(10年国債金利)は上昇すると予想しています。今回は、金利が将来上昇するものとして、話を進めたいと思います。では、今後金利が上昇すると考えるならば、店舗型ビジネスにはどのような施策が必要とされるのでしょうか。
それは、ずばり
客単価を引き上げる施策
ではないかと思います。その理由は、
金利上昇→支払い金利の増加→売上金額の拡大が必要
だからです。支払い金利の増加までは、特に問題ないと思います。P/Lで言えば、営業外費用の支払利息が増えることになります。経常利益額を同じだけ稼ぐためには、支払利息が増えた分だけ売上を増やす必要があります。だから、売上金額の拡大が必要になるのです。
もちろん、支払利息が増えた分だけその他の費用を減らせば、経常利益は同じ金額を確保できます。しかし、円安による原材料高や人口減少による人件費高は、今後も続く可能性が極めて高いので、その他のコストを削減することはとても難しいのではないでしょうか。だから、売上拡大が必要なのです。
売上を増やす方法は2つ。客単価を引き上げるか、客数を増やすかの2つです。客数を増やすという方法も、もちろんあります。しかし、これは難しい。その理由は、人口が減少しているからです。人口が減少していても、客数を増やすことは可能ですが、そのためには、競合他社より顧客を奪わねばなりません。そのためのコストがバカにならず、逆に利益率の低下を招きかねません。
客数増によって既存店売上を前年同期比でプラスを達成した国内ユニクロ事業が、まさにこの事例にぴったりです。既存店売上がプラスになったのは、客数が大幅に増えたから。しかし、客数が増える一方で、客単価が大幅に減少するという事態に直面しています。その結果、国内ユニクロ事業は減益。支払金利の増加分を相殺するために売上拡大を目指した結果、減益になれば、何をしているのかわかりません。客数増による売上拡大は、極めて危険なのです。というわけで、売上拡大のもう一つの方法である客単価の引き上げが必要になります。
今回は店舗型ビジネス、しかも店舗数も少ない企業の場合を考えたのですが、これが製造業や大規模チェーンになれば、また別の方法もあります。規模の経済が働きやすい規模になれば、稼動力の向上や店舗数の増加によって、支払金利増加分の利益を稼ぐが可能になります。ただし、この場合シェアを拡大させる必要があるため、競合他社のシェアを奪わなければなりません。血みどろのレッドオーシャンを勝ち続けなければならず、そのハードルはかなり高くなります。
☆今日のまとめ☆
長期社債の発行が増えるのは、金利の先高感が強いから。
金利が将来上昇すると考えれば、客単価の引き上げによる売上拡大が必要になる。
というのは、支払金利増加分の利益を稼ぐ必要があり、そのためには客数ではなく客単価の向上による売上拡大が求められるから。
WSJを読むには、基本的な英単語を知っていなければなりません
☆ 今日のこぼれ話☆
最近の記事は、すべて予約配信にて執筆しています。
思いついたことや考え事があれば、それをテキスト化し、溜めているからです。
実は、今は9月4日。
大手企業による長期社債の発行急増から考えた、店舗型ビジネスがやるべき仕事とは?
長期社債の発行が急増しているようです。
国内企業の社債発行が活発になってきた。なかでも満期まで10年以上と長い期間の社債を発行する動きが目立つ。年央に大きく動いた長期金利が落ち着いてき た一方、市場では金利の先高観もくすぶる。このため、低金利の今のうちに長期資金を手当てしておこうという企業が増えている。(2013年9月4日付 日経新聞朝刊)
要は、今後金利が上昇するだろうから、低金利の今のうちに必要資金を調達しておこうという考えのもと、大手企業が社債の発行を増やしているということです。藤巻健史さんの言う
金利上昇時→短い運用・長い調達
という理論を、そのまま適応したことになります。
将来金利が上昇するのか、それとも下降するのかは、人によって予想は違うでしょう。個人的には、2%インフレを日銀が目標にしている以上、名目金利は理論上上昇するので、長期金利(10年国債金利)は上昇すると予想しています。今回は、金利が将来上昇するものとして、話を進めたいと思います。では、今後金利が上昇すると考えるならば、店舗型ビジネスにはどのような施策が必要とされるのでしょうか。
それは、ずばり
客単価を引き上げる施策
ではないかと思います。その理由は、
金利上昇→支払い金利の増加→売上金額の拡大が必要
だからです。支払い金利の増加までは、特に問題ないと思います。P/Lで言えば、営業外費用の支払利息が増えることになります。経常利益額を同じだけ稼ぐためには、支払利息が増えた分だけ売上を増やす必要があります。だから、売上金額の拡大が必要になるのです。
もちろん、支払利息が増えた分だけその他の費用を減らせば、経常利益は同じ金額を確保できます。しかし、円安による原材料高や人口減少による人件費高は、今後も続く可能性が極めて高いので、その他のコストを削減することはとても難しいのではないでしょうか。だから、売上拡大が必要なのです。
売上を増やす方法は2つ。客単価を引き上げるか、客数を増やすかの2つです。客数を増やすという方法も、もちろんあります。しかし、これは難しい。その理由は、人口が減少しているからです。人口が減少していても、客数を増やすことは可能ですが、そのためには、競合他社より顧客を奪わねばなりません。そのためのコストがバカにならず、逆に利益率の低下を招きかねません。
客数増によって既存店売上を前年同期比でプラスを達成した国内ユニクロ事業が、まさにこの事例にぴったりです。既存店売上がプラスになったのは、客数が大幅に増えたから。しかし、客数が増える一方で、客単価が大幅に減少するという事態に直面しています。その結果、国内ユニクロ事業は減益。支払金利の増加分を相殺するために売上拡大を目指した結果、減益になれば、何をしているのかわかりません。客数増による売上拡大は、極めて危険なのです。というわけで、売上拡大のもう一つの方法である客単価の引き上げが必要になります。
今回は店舗型ビジネス、しかも店舗数も少ない企業の場合を考えたのですが、これが製造業や大規模チェーンになれば、また別の方法もあります。規模の経済が働きやすい規模になれば、稼動力の向上や店舗数の増加によって、支払金利増加分の利益を稼ぐが可能になります。ただし、この場合シェアを拡大させる必要があるため、競合他社のシェアを奪わなければなりません。血みどろのレッドオーシャンを勝ち続けなければならず、そのハードルはかなり高くなります。
☆今日のまとめ☆
長期社債の発行が増えるのは、金利の先高感が強いから。
金利が将来上昇すると考えれば、客単価の引き上げによる売上拡大が必要になる。
というのは、支払金利増加分の利益を稼ぐ必要があり、そのためには客数ではなく客単価の向上による売上拡大が求められるから。
WSJを読むには、基本的な英単語を知っていなければなりません
☆ 今日のこぼれ話☆
最近の記事は、すべて予約配信にて執筆しています。
思いついたことや考え事があれば、それをテキスト化し、溜めているからです。
実は、今は9月4日。
